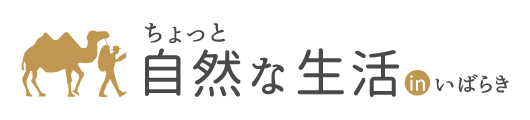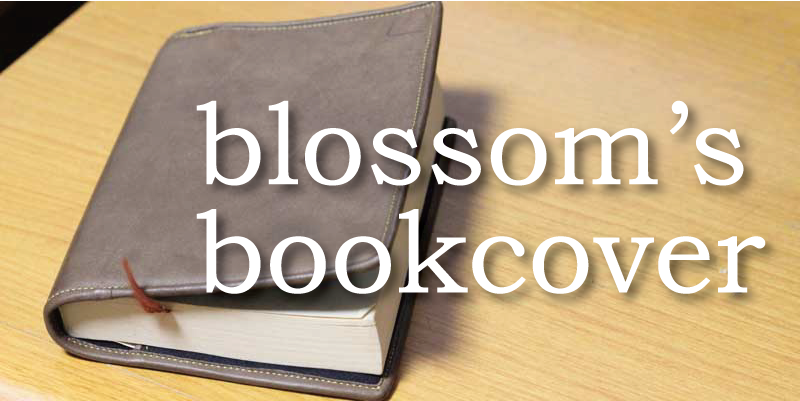羊革で作ったブロッサムのブックカバーの触り心地がとてつもなく良い。
★本が好き、ブックカバーも好き
私は本好きを自称している割に、いくらも本を読んでいない。いわゆる読書家では決してない。その割にいくつも本棚があって、そこには本がぎっしりと詰まっているが、貴重な本を集めているという訳でもないから、蔵書家でもない。それでも、「本が好き」と思い込んでいるから、本にまつわる小道具は欲しくなる。
しおりだったり、ブックカバーだったり。
文庫を読む時はたいていブックカバーをして読む。屋外で読むことは少なくて、寝る前に読むくらいなものであるが、それでも文庫を読む時はブックカバーをする。お気に入りのブックカバーをつけると、読書欲がわく……気がするから。
ブックカバーもいいのを見つけるとついつい手が伸びてしまう。だから、一つ二つあればいいものを、いくつもブックカバーを持っている。ミンサー織のブックカバーだったり、カラフルなブックカバーだったり、気に入った書店で売っていたブックカバーだったり。
最近買った文庫のブックカバーが偉く気に入っている。
それは、オーダー革手袋専門店のブロッサム(東京都多摩市)の革のブックカバー(文庫用)だ。
★ブロッサムのブックカバー
ブロッサムでは羊の皮使った革製品作っている。中でも革手袋が有名で、ブロッサムの看板商品だ。
「もともとはゴルフグローブ専門で作っていたの。そしたら、ゴルフやらない人がいい革ねいい革ね! 普通の手袋も作ってくれない?っていうので始まったの」
ブロッサムのオーナーの加藤さんが言う。その後、ブロッサムは雑誌やテレビなどで紹介されて、加藤さんはちょっとした有名人らしい。
ブロッサムのブックカバーを初めて見たのは、生活クラブの展示会であった。そこにブロッサムが出展していて、ブースにはいろいろな革製品が並んでいた。その中に、ブックカバーを見つけるとすかさず手に取った。すると、今までのブックカバーと肌触りがまるで違う。ふんわりとしていて、指を包み込むかのようにやわらかい。
なにこれ、すごい!と加藤さんに言うと、ふふふっ、すごいでしょと不敵な笑みを浮かべる。
革のブックカバーを持ってはいたが、それとはまるで違う。同じ革なのになぜだろう? 羊の革だから?
「このブックカバーはね、ちょっと仕掛けがしてあって……」
やっぱり仕掛けがあったのか! 道理で普通の肌触りではないと思った。
「羊の革と生地の間に、もう一枚生地が挟まってるのね。その生地に小さい穴がいっぱい空いていて、そこに空気がすぅっと吸い込まれるようになるので、余計柔らかく感じるの」
話を聞いても原理はよくわからないが、とにかくすごい仕掛けなのだろう。
「たくさん手が触れるじゃない?ブックカバーって。だから生地を足して丈夫にしているのもある。それと触った時にふわ~っと感じる気持ちよさが出る。羊の革の良さを表すのに、ちょうどこのやり方がいいのかなって」
なるほど、この肌触りの良さは特殊な作り方にあったのか。加えて触り心地が良いだけではなく、丈夫でもあるという。
「実用新案権も取ったんですよ」
じゃあこの作り方はブロッサムさんオリジナル?
「そうだね。別に誰がやってもいいけどね(笑)。でも、誰かがやって先に権利取られると困るからね。だから一応」
あー、そういう悪知恵が働く人いそうですね。
「革の質もあるけれど、場所もあるんだよね。羊のお腹の皮が一番やわらかいんだよ。背中っていうのは骨がごりごりしているから、角質化して硬くなっちゃう。お腹のところでも骨に接しているところは硬いから、そこは外していいところの皮だけ使っている」
他でこういう作り方しているところはあるんですか?
「恐らくないですね。皮が勿体ないですからね(笑)。羊もね、生まれて半年以上経っている羊を使っているの。あまり小さすぎても効率が悪いじゃん。大きく育ちすぎると皮が固くなるってのもある」
へぇ~~~。
「あとね、エチオピア産っていうのもいいんだよ。エチオピアで生まれて育ったのがいいの。エチオピアっていうのは気候がね、違うんですよ。温度が昼は高くて夜は寒いの。それがね、羊にとっていいんだよね」
野菜や果物も寒暖差があるといいのが育つっていいますよね。
「そうそう、革にとってもいいんだよね。丈夫に育つから」
やっぱりゆるい環境でぬくぬくと育てられたのは……。
「ダメなんだよ(笑)。人間と同じ(笑)」
ゆるい環境でぬくぬくと育ってきた私の心に突き刺さる言葉であった。