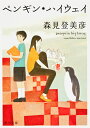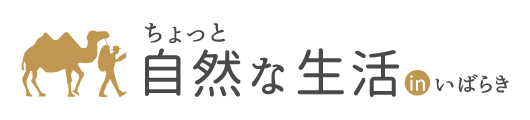過ぎ去った少年時代の記憶が蘇るファンタジー文学
私が小学生の頃、家のすぐ近くに雑木林があった。その林は住宅地と住宅地の狭間にあって、子どもだけでその林を抜けるには少しばかりの勇気が必要なくらいの、それなりに広い、鬱蒼とした森林であった。
その雑木林に、私は友人たちと「基地」を作った。基地といっても、特別何かがある訳ではない。屋根がある訳でもないし、囲いがある訳でもない。ちょっとだけ広々としていて、伐採後の木を椅子替わりにして座ることができるくらい。
私たちはその基地で、漫画雑誌やらを持ち込んでそこで読んだり、そのへんに落ちている木の棒を「剣」に見立てて振り回して遊んだり、しているだけだったが、子どもにとっては家や学校とは別にそのようなスペースがあることが、とてもとても、大事な楽しみのひとつだった。
基地は特別な場所であったが、そこで特別なことをする訳でもなかった。その場所にいるだけで、特別だったから、満足だった。
いや、一つ特別なことがあったな。それは、道端に落ちているエロ本を拾って、基地で読んだこと。時は昭和後期から平成初期。その頃は令和ほどホワイトな世の中ではなく、当たり前のようにそのへんの道に漫画雑誌やら週刊誌やらが捨てられていて、ごくまれにそれが「エロ本」のことがあった。特別な場所「基地」で行う、特別な行為「エロ本を読む」。その時の私たちの感情の高ぶりといたら、それは、もう。
そんな基地での日常は、突然失われることになる。ある日、近所の小学校高学年の悪ガキからの襲撃に遭う。高学年の連中は、その雑木林でサバイバルゲームをしていた。「ここは俺たちの場所だ」みたいなことを言われたような気がする。高学年が手に持っているのはBB弾を発射するモデルガン。私たちが手に持っているのは木の棒(気持ち的には勇者が持つ剣なのだが)。歯向かったところで、結果は目に見えていた。
森見登美彦さんの「ペンギン・ハイウェイ」読むと、そんな私の幼き頃の冒険(基地と闘争)、そしてファンタジー(エロ本)の記憶がまざまざとよみがえってきた。
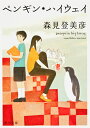
以下、ネタバレ含む感想である。
ペンギン・ハイウェイの主人公は小学4年生のアオヤマ君。この少年がだいぶおませさんで面白い。たくさんの書物を読み、ノートに記録をし続け、独自の研究を進めている研究者のような小学生。オトナ顔負けの知識と語彙力を身に着けており、たいへんな努力家である。その努力の積み重ねが自信につながっているのか、いつも冷静沈着で堂々としていて小学生らしからぬ小学生である。森見さんが描くいつもの主人公「腐れ大学生」とはまたちょっと違う感じ。森見さんの小学生時代はひょっとしたらアオヤマ君みたいだったのかな、なんて思った。
物語の進行に大きな役割を持つのが、大人の魅力と不思議さを併せ持つ歯医者のお姉さん。アオヤマ君は彼女のオッパイと彼女自身に不思議な感情を抱くが、それがまだ何かわかっていない。この物語は、少年と不思議な女性との純愛物語でもある気がする。
アオヤマ君とお姉さんの純愛パートの他に、アオヤマ君が通う小学校の友人たちとの話「小学校パート」がある。アオヤマ君の唯一無二の親友・ウチダ君はドラ〇もんでいうところののび太君ポジションにあたる。しずかちゃんポジがハマモトさん、ジャイアンポジがスズキ君、スネ夫ポジはスズキ君の子分二人(適当)といったところか。
ハマモトさんがまたおませさんな小学生で、しずかちゃんとはキャラ被ってないのだけれど、まぁポジション的にはここに収まるかと。いいとこの出生なのはしずちゃん同様なんだが、彼女よりも勝気で活発、アオヤマ君同様に研究熱心。それでいて、好きな男の子に対してのアプローチが小学生らしくかわいらしい。お姉さんとは違った魅力があり、私はどちらかというとハマモトさん派だった(ロリコンではない)。
そのような「小学生の世界」のテンプレに、アオヤマ君という異質な、小学生らしからぬ主人公が加わっているのが「ペンギン・ハイウェイ」の世界である。肝心のドラ〇もん枠はお姉さんかな。四次元ポケットみたいな不思議な能力あるし。
彼らが登場する小学生パートで、おじさんの心をくすぐるノスタルジーなことが次々に起こる。
「探検」と称して街中を歩き地図を作ったり、川の水源を探して川沿いをひたすら歩いたり。川沿いを歩く描写は、とてもシンプルに描いているのだけれど(森見さんらしからぬ)、それがまた児童文学っぽくていい。過去に読んだ「鉄塔武蔵野線」を思い出した。鉄塔を辿ってひたすら歩く「鉄塔文学」。そういえば「鉄塔武蔵野線」もファンタジーノベル大賞受賞作。森見さんも「太陽の塔」で同賞を受賞している。
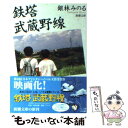
探検先で、アオヤマ君は「基地」を作る。基地といっても、持ってきた毛布を広げただけのスペースだ。そこで、お母さんが水筒に入れてくれた紅茶を飲んだり、ノートに何か書いたり、休憩をしたりする。私が過去に作った基地とそう変わらない。アオヤマ君の基地の方が、毛布があるだけ立派で、移動式であることが優れているが。
やがて、基地はある場所に固定されて「観測ステーション」として立派になる。パラソル、椅子、ハンモックなどが置かれ、双眼鏡で観察するなど、機能的にもかなり基地らしくなる。
私が作った基地は「20世紀少年」のケンヂたちが少年時代に作った基地程度であったが、アオヤマ君らが作ったのはそれ以上で、「ぼくらの七日間戦争」の基地未満、といったところか。※ぼくらの七日間戦争の基地をあまり覚えていないけれど。映画の主題歌(B.B.クイーンズの)のインパクトがすごかったのだけは覚えている。

また、ジャイアン・スズキ君軍団との闘争があったり、時折、お姉さんが出てきてオッパイというオトナの魅力をふりまいたり……「ペンギン・ハイウェイ」には自分自身の小学生時代をフラッシュバックさせられて、少年の心に強制的に戻されることがしばしば。
他にもアオヤマ君の妹やウチダ君が「死」に対して怯える場面があるのだが、私も小学生の時、同じような不安に駆られたのを思い出す。
あと数年したら中学生になり、その先は高校生になり、やがてオトナになって仕事をしなくてはならない。今は父や母が当たり前のように世話をしてくれるけれど、やがて二人は「死」んでしまう。この世からいなくなってしまう。それってどういうこと? 父や母だけではない、やがては自分自身も死ぬのだ。死んだらどうなるのだろう……。下校の時に、そんなことを考えて歩いていたらとても心細くなり、訳がわからなくなり、泣きたい気持ちになった。「死」への意識。個人差はあるだろうけれど、これも多くの小学生が通る道ではなかろうか。
「基地」と「探検」、「異性」と「死」への意識。私も小学生だったころに経験したことを、なぞるように物語は進み、そこに「ペンギン」が交わっていく。中盤から後半はファンタジー要素がやや強め。
その中に森見さんらしさも健在で、特に淡々とやや冗長に森見節が長々と語られたあとにやってくる怒涛の展開から得られるカタルシス(「太陽の塔」でいうと「ええじゃないか」)もクライマックスのペンギン大量発生のあたりで感じられた。
私の基地があった雑木林は、伐採されて住宅が建ち、跡形もなくなくなった(もともと形と呼べるほどのものがある基地ではなかったけれど)。戻りたくても戻れない基地、そして少年時代。物語のラストでは、アオヤマ君は失ったもの(人)との再会を信じて終わったが、私は過ぎ去った過去がもう一度やってくるとは当然思わない。
けれど、この「ペンギン・ハイウェイ」を読み返すことで、その時の心情は蘇る。少年時代を思い起こすために本棚に置いておきたい本である。