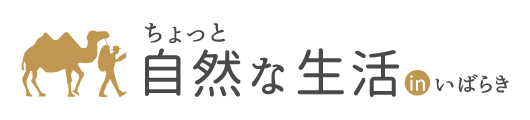江戸時代後期に活躍した戯作者・十返舎一九の代表作「東海道中膝栗毛」
2025年の大河ドラマ「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎の奉公人でもあった十返舎一九は、文章も絵もこなす多彩な作家であったそうな。同時代に活躍した曲亭馬琴(代表作・南総里見八犬伝)や山東京伝(洒落本)とは趣の違った、軽快で大衆的な作風で大いに笑わせてくれる。一九最大のヒット作になった本作は、蔦重亡き後に出版された作品である。
阿呆な私は、蔦屋重三郎も十返舎一九も弥次さん北さんも、その名を知ってはいたが、それ以上の知識はなかった。「弥次さん北さん」で私が真っ先に思い浮かんだのが、「真夜中の弥次さん喜多さん(しりあがり寿)」、「御存知 弥次喜多珍道中(ファミコンのソフト)」というのだから、お察しくだされ。
スポンサーリンク「べらぼう」が始まったのを良い機会に、本棚に挟まってた「池田みち子の東海道中膝栗毛」を手に取って読んでみたところ……面白いではないか! 行く先々の宿で弥次北が夜這いをしかけたり、盲人や子どもを騙したりとろくなことをしないのだが、それが悉く失敗してしまうのが実に滑稽だ。
弥次北の阿呆な行動に(よせばいいのに)と心配しつつも、結局は痛い目にあう二人に笑ってしまう。そして、〆の狂歌を詠む。この決まったパターンを繰り返しながら、江戸から伊勢神宮までの「膝栗毛(徒歩の旅)」をしていく。
私が読んだのは故・池田みち子さんの現代語訳版で、とても読みやすかった。岩波文庫の原文にもチャレンジしたが、私にはちょっと読みにくかった。他の現代語訳版では、伊馬春部さん(岩波文庫)のものが有名らしい。
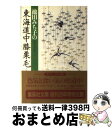
失敗を重ねる弥次北を(どうしようもないな)と馬鹿にしながら読んでいたが、男の二人旅なんていうのは、こんなものかもしれない、とも思う。かくいう私も何度か男二人旅をしてきたが、どれも失敗ばかりだったことを思い出す。
タイに男二人で旅した時は、私の勝手な行動から喧嘩になり、単独行動をして詐欺に引っ掛かりそうになったり。沖縄では、相方のマニアックな趣味に付き合わされて辟易したり(せっかくの沖縄旅行なのに訳の分からぬB級スポット巡りに付き合わされた)。近場の山旅では、山の後の温泉で相方が身体を洗わずに湯舟につかる様を見てカルチャーショックを受けたり。
普段は親友だと思っていた友人が、旅になると価値観の違いがあらわになって、若さゆえにそのギャップを消化できずにヤキモキしてしまった。で、旅行の後に疎遠になってしまうことが多かった。まぁこれは、男同士に限らずとも、異性であっても同じことが言えるのだけれど。
その点、弥次さん北さんは、互いに出し抜こうとはするものの、人間性が近いものがあるのか(いわゆるクズ的な)大きな喧嘩にならない。このような関係性をちょっと羨ましく思うと同時に、では私と旅した友人たちとの間に何が足らなかったかというと、それは狂歌であることに気づく。
弥次さん北さんは失敗を狂歌にして詠み、あははと笑ってケロリとしていた。私たちにも狂歌のようなものが必要だったのだろう。人と人との関係なんて、鏡花水月のようなものだから。
※表紙の写真はイメージです。2016年の江の島の写真で東海道の写真ではありません。
東海道中膝栗毛の本
私が読んだ池田みち子さん現代語訳の「東海道中膝栗毛」。中古本です。
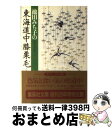
伊馬春部さん現代語訳の「東海道中膝栗毛」。今度読んでみようと思います。


十返舎一九原作の「東海道中膝栗毛」。