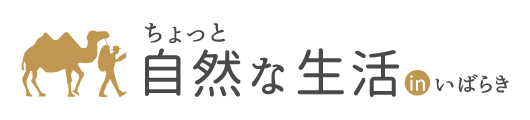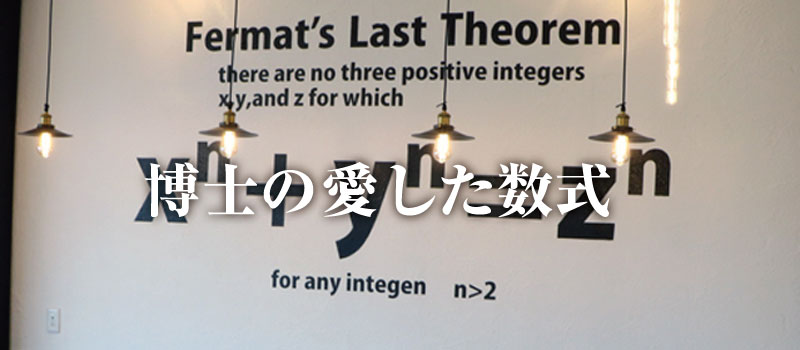数学が苦手な私でも読める「数式」の本
先日、友人のおっさんが新しくお店を開いた(雇われ店主)。小ざっぱりしていて、ちょっとオシャレなカフェだった。シンプルでシックな内装の壁に、でかでかと描かれていたのがフェルマーの最終定理だった。
xの三乗+yの三乗=zの三乗
無学な私はそれがフェルマーの最終定理と知らず「なんすか、これ。なんか意味あんすか」とおっさんに尋ねた。
「それはねぇ、フェルマーの最終定理だよ」
フェルマーの最終定理。それが何のことがまったくよくわからないが、言葉だけは知っていた。つい最近もこの言葉を耳にしたばかりだった。
「博士の愛した数式」を読み始めたんだよ。
私が同居の母にそう報告したところ「ああ、なんだっけ。フェルマーの最終定理とか出てくるんだっけ」と母が言った。
フェルマーの定理。それが何のことがまったくよくわからないが、言葉だけは知っている。何で言葉だけ知っているのかもわからないくらいにわからない程度の知識だった。
「この店の出資者が好きらしいんだよね。フェルマーの最終定理とやらを」
カフェのおっさんはそう言った。
ジャストじゃん、ちょうど今「博士の愛した数式」を読み始めたんですよ! と熱っぽく語りたい気分になったが、おっさんは小説を読まない人だったのでその報告をしたところでわかるまい。熱を心の中にしまい込み、出されたパスタを頬張った。
私の今読んでいる本とおっさんのカフェがつながったのには驚いたが、もっと驚いたのが、注文もしていないのに勝手にパスタが出てきたことだった。長い付き合いとはいえ、一応客だぞ、食べるものくらい選ばせてくれ。


数学をこよなく愛する、記憶が80分しか持たない老人「博士」。彼に出会った一人の家政婦とその子ども「ルート」は、その影響を受けて次第に数学の素晴らしさ、美しさを理解していく。物語は、数学と阪神タイガースを題材にしながら、博士とルートと主人公=家政婦の暮らしを描いていく。
私は「博士の愛した数式」がどことなく先日読んだ「首里の馬」と似た雰囲気を持っているな、と感じた。作中では「世の中の役に立たない」と書かれていた数学だが、実は高度な数学は世の中の重要なところで、そこに数学の力が働いているとはわからないが、日常的に活躍しているどころか、なくてはならない存在。
「首里の馬」のクイズや記録もそうだ。日常的には役に立たなそうで無意味に思えることでも、どこかで誰かにとってとても重要な役割を果たす存在。
そのような存在に、ひたすら、淡々と打ち込む人間が出てくるのは、共通点であり、そのような人々がとても愛おしく、かっこよく思えた。私は数学は苦手で、いや、中学までは得意だったのだが、高校で途端に勉強という行為自体から離れた生活を送っていたため、高校レベル以上の数学はまったくわからない(数学だけじゃないけれどね)人間なんだけれど、そんな私が、この「博士の愛した数式」で公式やら定理やら証明やら素数やらについて、事細かく説明された文章を読み、心地よく感じてしまい、あわよくば「数学って面白い」「数学ってかっこいい」なんて思うなんて。
また、両作品中には「孤独」が漂っているように感じた。二つの作品の孤独さは、少し違う感じもするが、博士の愛した数式にもどことなく漂っている。この本から感じられる孤独さは、家政婦が一人で子を産み、育ててきた歩みにも感じるし、博士の記憶が80分しか持たない、数学とだけひたすら向き合う姿勢にも感じる。「首里の馬」の孤独は、登場人物が悉く孤独だ。
さらに、両作品には「謎かけ」が読者に出されている。「首里の馬」では、「にくじゃが」「まよう」「からし」という謎かけが物語中で出されるが、その答えははっきりとは明かされずに終わる。
「博士の愛した数式」でも、「eのπi乗+1=0」というオイラーの公式が出てくる。これは物語上で、博士が残したメモに書かれていたもので、家政婦がこの意味を図書館で調べるが、オイラーの公式ということまでは判明しても、博士が何のためにこれをメモに書いたかまではわからないままで物語は終わる。
しかし、私はわかってしまった。この謎が解けたのだ(ネットのレビューに書いてあった)!
博士は数学の問題を「声に出して読んでみる」ことが大事と教えた。
「イーのパイのアイジョウたすイチはゼロ」
いっぱいの愛情?! そうか、いっぱいの愛情か! で、何? だから何?
このメモを未亡人が見たあと、未亡人は何かを悟り、それまで激高していたのに急に落ち着いた。そして、家政婦を博士の家の仕事に復帰させることまでした。「いっぱいの愛情」は誰に向けられたものだったのか、未亡人に対して? ルートに対して? みんなに対して? 結局わからないや。まぁいいか。
さて、最後の共通点を挙げとく。それは著者の小川洋子さん(博士を愛した数式)と高山羽根子さん(首里の馬)が、プロ野球ファンであること。小川さんは「博士を愛した数式」でそのファンっぷりをこれでもかと発揮している。阪神の往年の名選手から(江夏、村山とか)、物語当時の名選手(亀山、新庄など。読んでいて亀山超懐かしいと思った)まで、固有名詞をこれでもかと書いている。
高山さんの「首里の馬」では野球ファンの様相は現れていなかったが、他の作品では出ているのかな(と、我が家で発令されている本購入制限を無視して「オブジェクタム/如何様」をアマゾンでぽちっと購入)。


そして、この本の奇妙なところが登場人物の固有名詞が出てこないこと。主要な登場人物は、博士とルートと未亡人と書かれ名前が明かされることはない。物語は主人公の家政婦の一人称で書かれているのだが、家政婦が人から呼ばれる時は「君」「ママ」。その代わり、数学者の名前や野球選手の名前は実名で表記されている。
これが読み手にとってどんな影響を及ぼすのか、作者は何の意図でこうしたのか。これもわからんままだったな。
「あー、わかんない、もう嫌だ!」
私は問題がわからないと、最後までやり遂げずに投げ出すタイプだった。投げ出してモヤモヤしなかった訳ではないが、そのモヤモヤを感じなかったふりをして漫画を読むなどしていた。
「博士の愛した数式」で出題された様々な問題。数学の問題だけではなく、オイラーの公式のメモや登場人物の固有名詞が出ないこと。それらの問題の答えが出ないまま、本を読み終えたのだが。物語自体は、すっきりした読後感だった。
「ふぅ」とため息ひとつついて、私は本を閉じた。モヤモヤはやはり残った。子どもの頃の私であれば、そのままにしただろう。だが、大人になった私はインターネットという文明の利器を用いて、問題解明に勤しむのであったが、それでもやっぱりわからない。
これはあれか、読者の想像にお任せしますってあれか。そうだ、それが答えだ。適当な答えを導き出して、「博士の愛した数式」を読み終えた実感を無理矢理得る私であった(こんな風に適当だから今の私があるんだな)。