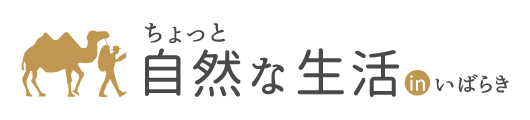「火薬画」で有名な世界的アーティスト・蔡 國強(ツァイ・グオチャン)と
いわき市の実業家であり、いわき万本桜プロジェクトの志賀忠重。
二人の生い立ちから出会い、そしてその成功への軌跡を描いたノンフィクション。
「空をゆく巨人」のあらまし
事実は小説より奇なり。
「空をゆく巨人」を読んで、真っ先に思い浮かんだのがこの言葉だった。
この作品は、世界的アーティスト・蔡 國強(ツァイ・グオチャン)といわき市の実業家・志賀忠重の二人が織り成すノン・フィクションの物語である。これが、そんじょそこらの小説よりも、ずっとスリリングで、ずっとダイナミックで、ずっと感動的で。
えーっと他にも、いろいろと考えさせるものがあったり、何かを学んだり。とにかく、とてもとても良い本だったのだ。
しかも、物語の舞台のひとつが福島県のいわき市で、いわき市といえば私が住む茨城県との県境にある市で、仕事やプライベートで何かと縁のある場所であった。
そんな馴染みが深く愛着のある町が舞台なのだから、物語の世界にもすぅっと入っていけて、尚且つ、水戸市にある芸術館の人や取手、高萩など、茨城県内の市町村名や人も度々登場してくるのだから、余計である。
さて、二人の物語は、その生い立ちから語られる。生まれながらの商売人の志賀と生まれながらのアーティストの蔡。青年期、いわきで次々と事業を成功させていた志賀と比べ、蔡は中国でもがき苦しんでいた。その時、蔡に一つの発想が生まれる。
それが、「火薬」だ。後に蔡の代表的なアート技法のひとつとなる「火薬画」によって、成功への足掛かりをつかむ。そして、私費留学先として日本を選び、いわきへ。志賀と蔡は出会い、そこからストーリーは大きく展開していく。
蔡の作品は世界に認められ、世界各国で個展を開くことに。北京オリンピックでは開会式と閉会式のビジュアル・ディレクターに起用されるほどの世界的なアーティストになった。
蔡の斬新で突拍子もないと思えるアート・プロジェクトに、志賀は事業家として、また作品の制作者として応えていく。志賀も志賀で、その商才をいかんなく発揮し、それで得た財力でもって、蔡以外の偉人もサポートするようになる。

北極海単独歩行編
その志賀の活躍ぶりが存分に描かれているのが、「空をゆく巨人」の中でも異彩を放つ章・第8章の「最果ての地」である。この章は、それまでの章と違って冒険小説の装いをまとった一つの作品になっている。
志賀は、冒険家の大場満郎と出会い、大場の冒険の支えをすることになる。大場の冒険とは、北極海の単独歩行。1730キロという途方もない距離を、海が凍っている間に歩いて、独りで渡るというもの。
その展開は、まさに冒険譚であり、スリリング極まりない。植村直己の本を読んでいるかのよう(実は未読だけれど)。私が読んだ本の中でいうと、「剣岳」とか。あとは、漫画の「岳」とか、映画の「エベレスト」とか、そのあたりか。遅読の私が、この「最果ての地」ばかりは一気に読まずにはいられなかった。
スポンサーリンクいわき万本桜プロジェクト(いわき回廊美術館)編
そしてもうひとつ、特筆すべきは12章から15章(最終章)の「いわき万本桜プロジェクト編(勝手に命名)」であろうか。
このプロジェクトは、東日本大震災後のいわき市の里山に、9万9000本の桜を植樹しようというもの(世界最大)。9万9000本という途方もない数字を植え終わるのは、何と250年後だという。桜の植樹は2020年12月現在も続いていて、2017年時点では約4000本の桜が植えられている。
このようなプロジェクトを発案するのは、やはり世界的アーティストの蔡なのか?と思いきや、実は志賀である。きっかけは、2011年3月11日に起きた東日本大震災と、それによる原発事故だ。
放射能により汚れてしまった故郷、病人のように元気をなくした知人・友人たち、そして、事実を報道しないメディア。他県の人は、みな口をそろえて「福島には放射能が怖いから行きたくない」と言う。志賀は、震災直後にボランティアをしながら見た光景に、現実に、怒りを覚えた。
そして、震災から一か月後。福島県に桜の季節がやってくる。それを見た志賀は、多くを失った故郷に、世界に誇れる場所を作りたいと思った。
それが、桜だった。その時に、蔡の言葉が頭をよぎる。
「99という数は無限の意味を持っています。100は完結し、99は永遠に続いていきます」
(空を行く巨人より引用)
桜の数は、9万9000本に決まる。9900本でなかったのは、桜の名所である京都の吉野山に植えられた桜の本数が約3万本であり、「どうせなら世界一がいい」ということもあって、それを超える数が設定がされた。
こうして、志賀による「いわき万本桜プロジェクト」がスタートし、いわき市の山に桜の植樹が始まった。震災と原発事故の被害に遭った方々が、思いを込めて桜を植えていく。
しかし、この物語はここで終わらない。「空をゆく巨人」は前述したとおり、蔡と志賀の物語である。蔡がこの万本桜プロジェクトに関わることで、二人の最大の共同作品が生まれるのだ……(続きは本編にて)。
この12章から15章にかけての、著者の川内有緒さんの文章の熱量がすごい。この熱量は、恐らく川内さんのものだけではない。志賀と蔡、いわきチームの人々や震災被害にあった人々、みんなの想いが、文章に乗っている気がした。
「プルトニウム(放射性物質)の半減期は2万4000年。一回ちょっとミスすれば、2万4000年も(回復に)かかるんだ」(空を行く巨人より引用)
志賀のこの言葉が、私の心に爪痕を残す。
そうなんだ、私たちだって、一度は同じような情報を目にし、耳にしているはずなんだ。でも、それが日常にすっかり飲み込まれてしまっていて、今はまた別の報道(情報)=コロナによって霞んでしまっている。
震災から数年経った時、私は仕事で福島の「人が住めない地域」に行ったことがある。
そこは、ゴーストタウンだった。倒壊した家、車は当時のまま、庭は荒れ放題。町の形をしているのだが、人の気配がない。その町にいるのは、除染関係の仕事をしている人と警察官の人だけ。何か動いたと、その方向を見てみれば、子連れの猪だったり、猿だったり。
当時の光景は、今も私の記憶に確かに残っているのに。(シートベルトをし忘れて警察に捕まった記憶も)
2020年現在も、「人が住めない地域」は存在している。
同時に、蔡と志賀の二人が作った「作品」も、いわきに存在している。
震災と原発事故の残した爪痕は甚大なものであるが、二人が残した希望の光もまた、とても大きく、温かく、忘れてはいけないことを思い出させてくれる貴重な存在になっている。
この二つの事実は後世に語り継がれるべきコトであり、そして、この二つの事柄を丁寧に記した「空をゆく巨人」にもまた同じことがいえるだろう。
今回紹介した本
- 出版社 : 集英社
- 著書 : 川内有緒
- 発売日 : 2018/11/26
- 単行本 : 372ページ

●川内有緒さんの本
スポンサーリンク