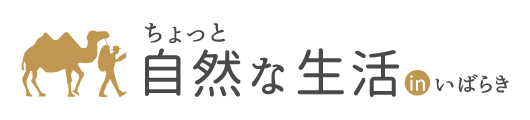中年と柴犬
犬が好きな人を犬派、猫が好きな人を猫派なんて分けることがあるが。私は犬派であり、かつては犬派の代表を狙うほど、とは言わないまでも、犬派の会合があれば行ってもいいかな、いやでもやっぱりめんどくさいな、と思う程度の犬好きであった。要するにそんなに犬好きでもないけれど、以前に犬を何匹も飼っていたものだから、自然と犬に対しては好意を抱くようになった。
特に、柴犬。君らは犬の中の犬だ。散歩の時におしりふりふりしながら歩く姿の愛しさといったら。飼い主にはデレデレなのに、見知らぬ人が来ると牙をむき出しにして唸ったりやかましいほどに吠えたりするツンデレぶりといったら。今でも柴犬を見ると犬を飼いたくなってしまうが、イマイチ踏ん切りがつかない程度に、柴犬のことは好きである。
スポンサーリンク
柴犬は2度ほど飼ったことがあって、他の犬種よりも思い出が多い。小学生のころ、友人が家に遊びに来て、我が家の犬を触っていたら犬が突然キレだして、友人の手をガブリとやった。友人の手から血が出ているのが見えて、焦った私は「何やってんだよ!」と友人の頭を叩いた。いや、どう考えても犬をるべきだろうに。
大人になってから飼った柴犬は、あまり世話をしなかったから、私にはなかなかなつかなかった。仕事から帰ってくると、ワンワンと吠えられることがしばしばあった。嬉しくて吠えているのではないことは、鳴き声からわかった。
その柴犬2号を飼っているころに、親父が死んだ。犬を可愛がっていたのは、主に親父だった。親父は病院で亡くなったのだが、少しして家に遺体となって帰ってきた。1階の寝室に、親父の遺体を寝かせた。その時、外で姉か誰かが柴犬2号の鎖を外した。すると、犬は家の中に上がり、親父のいるところまで走ってやってきた。普段は家の中には断固として入れない躾をしていたから、私がふざけて犬を家に入れようと仕向けても、柴犬2号は決して家に上がることはなかったのに。犬は親父の姿を見ると、せっせと外の犬小屋に戻った。
両方の柴犬の死に際は、今でもはっきりと覚えている。最初に飼った柴犬が弱ってしまったころ、私は東京に暮らしていた。
「犬がもうすぐ危ないかも」
親からの電話を聞いた私は、すぐさま電車に乗って水戸に帰る。私が家に着いたと同時に「くぅん」と小さく鳴いて犬は逝ってしまった。私が帰るまで待っててくれたのだ。もう少し、一緒に過ごしてやればよかった、と今でも悔やんでいる。
柴犬2号は、父が亡くなり私と母が二人で暮らしている時に亡くなった。お腹に水が溜まってしまう病気だった。散歩に行ってもあまり歩かなくなり、そのうち寝たきりになってしまった。病院に連れて行くと、処置をしてくれている獣医に牙をむいて反抗した。
「口を抑えてもらっていいですか?」
と獣医に言われる。
「え、俺が?」
私はビビりなものだから、飼い犬の口を手で抑えることを怖がった。小学生のころ、犬に噛まれた友人が手から血を流す姿が思い浮かんでしまう。
「飼い主さんなら大丈夫ですよ」
獣医にそう言われると、私がやらねば世の飼い主さんの名が廃る。必死の思いで、飼い犬の口を手で抑えた。
柴犬2号の最期のころは、家の中で一緒に過ごした。家の中と言っても玄関だけれど。玄関に段ボールやら毛布やらを敷いて、犬の居場所とした。一度、玄関のあがりくちのところまで犬をあげて、一緒に寝たことがある。家飼いの犬にとっては珍しくないことだろうが、我が家の犬にとっては特別なことだった。
……こうして犬についてツラツラと書いていると、犬が飼いたくなる。やっぱり私は犬派だ。犬派の代表を務めることや犬派の会合に出席することは無理でも、犬派の末席にちょこんと座るくらいには犬派なのだ。
最近では家の前をうろちょろする野良猫をうっとうしいと感じる素振りを周囲には見せながら、内心(猫ってかわいいな、こんなにかわいかったのか、飼いたいな)と思うようになっている。猫にうつつを抜かしつつも、柴犬を散歩している人など見ると、(やっぱり柴犬だよなぁ)と犬派であることを再確認する。
死ぬまでに、犬を飼う機会がもうワンチャンスあったらいいな(ワンワン)。

少年と犬 / 馳 星周
馳星周さんといえば「不夜城」が真っ先に思い浮かんでしまう。不夜城といえば裏社会の小説。馳星周といえば裏社会。そんな闇とか夜のイメージがある作家さんであったが「少年と犬」を読むと少しイメージが昼に変わる(「少し」ね)。作中、裏社会描写も出てくるのだが、どこか童話チックなのだ。
章ごとに展開される「犬」のストーリー。外国人窃盗団とその手助けをする男、関係の冷めた夫婦、娼婦、猟師の老人。口を閉ざした少年。それぞれが犬と関わり、みな幸福な思いをするのだが……その後に待っているものとは。
テンポの良い文章でサクサク読めてしまう直木賞受賞作。