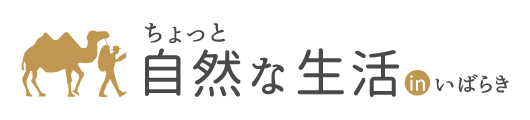北海道の農家の暮らしぶりを、笑いながら知ることができるコミック・エッセイ
荒川弘といえば
漫画家・荒川弘といえば、「ハガレン」こと「鋼の錬金術師 」である。この原稿を書いている新しいPCで、打ち込んだこともないのに「鋼」と打ち込んだ段階で「鋼の錬金術師」と候補に挙がってしまうほどに有名な漫画である。この漫画にハマった当時、「手合わせ錬成」やマスタングの指パッチンを真似してやってみたのは、今となっては良い思い出(当時30歳は過ぎていた)。ドラゴンボールのかめはめ波が本気で出ると思って真似していた幼少時代から、なんら成長がない。
また、漫画家・荒川弘といえば、「男性かと思っていたら女性だった」は荒川弘あるあるである。名が「弘」であるから、「ひろし」と読んで男性かとばかり思っていたが、この「弘」は「ひろむ」と読む。「ひろむ」でも男性のような名前であるが、実は女性。「本名から一文字省いたもの」が「弘(ひろむ)」の由来であるらしい。
そして、漫画家・荒川弘といえば、「農業」である。北海道出身で、実家は大型農場を経営。酪農をする傍ら、野菜も作っている。荒川さん自身も幼い頃から農業を手伝っており、その上農業高校に通っていた。荒川さんの「ハガレン」に次ぐ代表作「銀の匙 Silver Spoon 」は、農業高校が話の舞台になっている。
」は、農業高校が話の舞台になっている。
今回紹介する漫画「百姓貴族 」は、北海道の実家(農家)での経験や農業高校に通っていたころの話が描かれたコミックエッセイ。農家ならではの「あるある」が詰まっており(北海道ならではの部分も多い)、非農家ではあまり知ることができない、農家の暮らしぶりを知ることができる。
」は、北海道の実家(農家)での経験や農業高校に通っていたころの話が描かれたコミックエッセイ。農家ならではの「あるある」が詰まっており(北海道ならではの部分も多い)、非農家ではあまり知ることができない、農家の暮らしぶりを知ることができる。
農業産出額が長年にわたって一位の農業大国「北海道」だけあって、私の住む茨城県の農家と比べ(さすが北海道、スケールが大きいな)と感じる部分も多々あった。(畑がとんでもなく広く、冬に雪が積もるなど)
この「百姓貴族」の良いところは、農家の暮らしを「面白おかしく」知ることができるところかと。「農家」という家族形態ならではの、ちょっと荒っぽいやり取りや習慣は、もはや文化圏が違うと言っても過言ではなく、その違いを笑いを込めて描いてくれている。
その面白さの源が、荒川さんのお父さん=親父殿だ。破天荒な言動と行動は、私の抱く「農家の親父」のイメージそのものであり、その無茶っぷりが読んでいる側にとっては面白いのだ。(……が、当事者たちは大変なんだろうな)
農家の親父の思い出
私がかつて働いた農家の親父さんたちも、やっぱりエキセントリックな人が多かったように思う。
レンコン農家では、一応そこは会社になっていたので(一応とは失礼な)、農家の親父殿は「社長」と呼ばれていて、私も倣って「社長」と呼んでいた。「社長」と言うと、びしっとスーツを着て、偉そうで…(偉いんだけれど)、という子供じみたイメージをその頃は持っていたが、その「社長」はそうではなかった。
汚れてもいい服装で、いつも泥まみれだった(蓮田なんで)。厳しく指導はされたけれど、無駄に偉ぶっている感じではなかった。誰よりも朝早く起きて、私たちが休みの日も仕事をしていた。作業も誰よりも速かった。
社長というよりは、職人であった。
そりゃそうか、社長といっても小さな会社の社長だ。自分が率先してやらにゃ仕方ない。今ではそれがわかるけれど、その時はそうではなかった。
その農家の親父殿=社長は、何かと怒鳴る人だった(このへんがエキセントリック)。社長は怒鳴っているつもりではなかったのかもしれない、それが自然な口調だったのかもしれない。怒鳴られ慣れていない私は、それが嫌で辞めてしまった。(何ともヘタレである)
また、とあるメロン農家で働いた時は。そこは会社ではなく、いわゆる「農家」という感じであった。(法人化してたんだっけ?)実務は息子さんがしていて、親父殿は息子さんのフォローをしていた。メロン農家の親父殿は、とにかくよく喋る人で、よく笑う人だった。嫌なことがあっても、笑って吹き飛ばしてしまう、そんな感じの親父殿であった。
レンコン農家の親父殿は、あまり笑わない人だったので、対照的だった。失敗しても、「しゃあんめ(茨城弁:仕方ない)」と言って、済ませることも多かった。
どちらの親父殿も、仕事に対して綿密なようで、大雑把なようで、その辺の尺度がよくわからなかった。長年の経験によって、独特の感覚が身についているのだろう、ちょっとやそっと農業をかじった私になんて、わかるはずのない尺度である。
ちなみに、私はこの尺度を「農家の塩梅」と呼んでいる。親父殿たちは、今も元気で農業をしているのだろうか。
「百姓貴族」を読むと、農家の親父さんたちのことを思い出す。この本がそれだけリアルに農家の親父を描いている証拠だろう。
そして、農家の親父さんの顔と一緒に、農業を生業としていた当時の自分も思い出す。ああ、ヘタレだったな、考えが甘かったな、としきりに反省すると共に、いいことも思い出す。
夏の日の蓮田の風景だとか、きれいに咲いた蓮の花だとか、レンコンを初めて掘った日のこととか。
あたり一面がビニールハウスだらけの鉾田の風景だとか、お茶の時間に毎日のように食べたメロンだとか、夏になるとたまに出てくるスイカだとか。
この本は、その頃の私と今の私を、良くも悪くもつないでくれる「懸け橋」のような存在なのである。
今回紹介した本

- 出版社 : 新書館
- 著者 : 荒川弘
- 発売日 : 2009/12/11