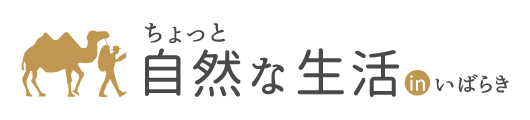父と百閒
私は電車というものが「何となく」好きだ。
「特に」好きな訳ではなく「何となく」だから、電車について詳しい訳でもなく普段から利用している訳でもない。でも、何となく好きだから、たまに乗りたくなる。
茨城県なんて場所は、どこに行くにも車があれば事足りる、というか、車がなければ仕方ない場所だから普段の移動は車だけれど、電車で行けるような場所は電車で行きたくなることがある。電車は目的地に行くための移動手段であるはずが、電車に乗ることが目的になることもある。
「なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う」
そんな時は、内田百閒の「阿房列車」をポケットに忍ばせて電車に乗りたくなるものだが、実践したことは未だない。私は百閒先生は大好きだが、百閒先生のような「電車好き」ではない。「何となく」程度に好きだから、電車に乗るのはたまにで良い。
けれども、私と電車は縁があるとは思っている。
というのも、亡き父はJRに勤めていたし、高校には電車で通っていた。東京に住んでいた時には毎日電車に乗っていた。それに周りには電車好きがちらほらといる。姉も昔は電車好きだったし、従兄弟には筋金入りの電車好き(あえてマニアと呼ばぬことにしよう)がいる。職場のボスも電車好きだというし、城里町の高萩さんは電車好きが高じて野菜の無人販売所に「やさいの駅」という名前を付けた。
他にも……電車、電車、電車と頭の中に「電車」を走り巡らせてみたが、私と電車を結ぶものはその程度だった。やはり、私と電車はそれほど縁がないのかもしれない。そう思った時、父と電車にまつわる出来事の記憶が蘇ってきた。
私が小さい頃は、父と一緒に電車で出かけることが多かった。JR社員は電車に無料で乗れるから、というのもあるが、何より父はペーパードライバーだった。茨城県に住んでいて、車に乗れないのは何かと不便であっただろう。
父は酒飲みだったから、電車内でよく酒を飲んでいた。今ではほとんど見なくなった光景だが、私が幼い頃(昭和後期から平成初期だろうか)では、電車内で酒を飲む人は珍しくなかった。
父は昼間でもお構いなしに、車内で酒を飲んだ。東京まで電車で通っていたから、帰りの電車では毎日飲んでいたようだ。友人たちと一緒の時は、ボックス席(4人座りの席)で皆酒を飲み、つまみを食べ、もはや宴会そのものだった。
ある日、父は幼い私を連れて電車に乗って出かけた。父はその時も酒を飲んでいて、私は酒臭い父の隣に座り、黙って外を眺めていた。すると、父が突然「何見てるんだよ」と怒気のこもった声を出した。
すぐ近くにいた若い男が、父を睨んでいたらしい。「なんでもねぇよ」と男は言い、「そうか」と父は返して事は収まったが、その時走った緊張感は未だに覚えている。喧嘩っ早い父のことだから、その時以外にもそんなことはあったのかもしれない。
またある日のこと。
これは、電車内の出来事ではないが、私が東京に移り住んでいた時に、父が仕事帰りに私に会いに来た。上野駅の近くの銀座ライオンあたりで夕食を共にした。その時、父が切り出した。
「仕事を辞めようと思う」
国鉄時代から務めたJRの仕事を辞めるという。当時父は60歳手前だったから、早期退職にあたるのか。
「そう、いいと思うよ」
父の思い切った告白に対し、私は何の考えもなしにそう言った。今思えば、父としては大きな決断をしたのだろうに、20歳手前の学生だった私は、そんな重要なこととは思わなかった。
酒好きで電車好きという点で、父と百閒先生には共通点がある(鳥好きという点でも似ている)。そういえば、顔もどことなく百閒先生に似ているかも……と思い、両者の写真を見比べてみたが、そんなことはなかった。それでも「強面」という点は一緒だ。父はいかりや長介に似ているとよく言われていた。
私と電車にはそれほど縁はないが、父と電車には縁があり、父と酒にも縁はある。すなわち、父と百閒先生は縁がある。随筆作品の中に登場する百閒先生に、父性を感じることがある。私は、百閒先生と父を、いつからか重ね合わせていた。
「阿房列車」シリーズは、百閒先生の作品の中でも特に好きな作品群だ。用事はないけれど、電車に乗って旅をする。お供を連れて、車内で食事とお酒を楽しんで、宿泊先でもお酒を楽しんで。ところどころで苦言を呈して、それがまた百閒先生らしいものだから、面白おかしくて。
こんな旅をいつかしてみたい。それにはまず百閒先生のように「先生」と呼ばれるようにならなくてはならない。たぶんそれは、一生かかっても無理だろうから、夢のような話である。ならばせめて、寝る前に阿房列車を読んで、夢の中で旅しよう。
阿房列車関連本

●百閒先生の阿房列車シリーズ
●「ヒマラヤ山系」こと平山三郎さんが書いた「阿房列車」にまつわるエッセイ
●酒井順子さんによる鉄道旅エッセイ
●阿川 弘之さんによる「阿房列車」のオマージュ作品
●交通学者・竹内伝史による異国版「阿房列車」の旅。
●乾正人さんの産経新聞連載作品を書籍化
●「阿房列車」の漫画版